
スマホとICレコーダを接続してYouTube音声をICレコーダに録音する方法
スマホで再生したYouTubeの音声をICレコーダーに録音する方法について、詳しく説明します。ICレコーダーがPCM録音に対応していない場合でも、スマホの音声を録音する方法を紹介します。
エンジニアが直面するキャリア・お金・女性・健康の問題を考えるサイト

スマホで再生したYouTubeの音声をICレコーダーに録音する方法について、詳しく説明します。ICレコーダーがPCM録音に対応していない場合でも、スマホの音声を録音する方法を紹介します。

LVDT(Linear Variable Differential Transformer)は、高精度な直線変位測定に使用されるセンサーです。本記事では、LVDTのシステム構成、動作の流れ、目的、そして含まれている機能について詳しく説明します。

絶縁回路の話の中で「にちょく」という用語が出てきました。 何のことやら意味が分からなかったので、調べました。 下記は、ChatGPT4Oによる回答です。 「二直(にちょく)」とは、電気回路や電子機器の絶縁に関する用語であり、英語では「Double Insulation」と呼ばれます。二直とは、特定の機器やシステムにおいて、一次側と二次側の間に二重の絶縁層を設けることで、高いレベルの安全性を確保するための設計手法を指します。

入力オフセット電圧(Input Offset Voltage)とは、オペアンプの反転入力端子(-)と非反転入力端子(+)の間に存在する小さな電圧差のことを指します。この電圧差がない理想的なオペアンプでは、両端子間に電圧差がゼロのときに出力電圧もゼロになるはずです。しかし、実際のオペアンプでは製造上の不完全性や内部バランスのズレにより、わずかな電圧差が存在します。

PI制御(比例-積分制御)は、伝達関数を用いて以下のように表されます:

伝達関数は、制御工学や信号処理の分野で非常に重要な概念です。一言で言えば、伝達関数は「入力と出力の関係」を数式で表したものです。しかし、この単純な説明だけでは深い理解が難しいかもしれませんので、もう少し詳しく、そして直感的なアプローチで解説します。

システムの帯域幅は、そのシステムが効果的に動作する周波数範囲を指します。制御システムやフィルター、アンプなどの電子機器において、帯域幅は通常、システムの応答が入力信号の周波数に対してどの程度良好であるかを示す重要なパラメータです。

抵抗とコンデンサを組み合わせて作る回路(RC回路)の時定数は、システムが外部からの入力変化に対してどれだけの時間をかけて反応するか、あるいはその反応が減少していく速度を示す指標です。具体的には、時定数はシステムが外部の入力に対して約63.2%反応する時間を示します。

RCフィルタの時定数(τ = R * C)が同じであれば、その回路のカットオフ周波数は同じになります。しかしながら、RやCの絶対値が非常に異なる場合、以下のような違いや懸念点が生じることがあります:
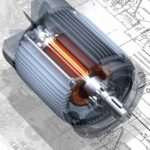
熱電対は、異なる2種類の金属または合金が接続され、その接続部分が温度差を受けると電圧が生じる現象(熱電効果)を利用して、その電圧から温度を測定する装置です。