電子機器の中には、電源を間違ってつないでしまったとき(プラスとマイナスを逆に接続する「逆接続」)に、回路が壊れてしまうものがあります。特に、DC/DCコンバータという電圧を変換するための重要なICは、逆接続に非常に弱く、壊れやすい部品のひとつです。
逆接続とは?
たとえば、次のようなケースを想像してください。
-
機器を2本の電線でつなぐとき、誤って+と−を逆にしてしまう
-
バッテリーや外部電源をつなぐとき、配線ミスで極性が反対になる
このようなとき、電源ラインに−10V、−24V、あるいは−48Vといった強いマイナス電圧が入る可能性があります。
逆接続がDC/DCコンバータに与える影響
DC/DCコンバータは、本来「正しい電圧範囲で、正しい極性で」動作するように設計されています。
多くのICは、−0.3V程度までしか逆電圧に耐えられません。
これを超えると、IC内部の回路が破壊されるリスクがあります。
解決策:「トランジスタによる低ドロップ型逆接続保護回路」
この問題を防ぐために回路に追加されるのが、「トランジスタを使った逆接続保護回路」です。
中でも、電源ラインの電圧降下を最小限に抑える設計を「低ドロップ型(low-drop)」と呼びます。
たとえば、「PチャネルMOSFET」と呼ばれるトランジスタを使うと、
-
正しい接続:MOSFETがオンになって電流がスムーズに流れる
-
逆接続:MOSFETが自動的にオフになり、ICへの逆電圧を遮断する
というしくみで、効率を落とさず、安全性を高めることができます。
ダイオードではだめなの?
逆接続保護にはダイオードを使う方法もありますが、
-
電圧を0.4~0.7Vほど消費してしまう(→効率が悪い)
-
電源が弱い(たとえば24Vループ回路など)と、電圧ドロップが致命的になる
といった理由から、最近はトランジスタ(MOSFET)による保護が主流です。
このような回路は搭載すべき?
結論から言えば、はい、搭載すべきです。
特に以下のような条件がある場合は、逆接続保護はほぼ必須といえます:
-
装置が現場で配線される(人手で電源をつなぐ)
-
2線式電流ループやバッテリー接続など、逆極性のリスクがある
-
製品の信頼性や安全性が求められる(たとえば産業機器やセンサ)
逆接続が一度でも起きれば、電源ICやDC/DCコンバータが即座に破損し、
最悪の場合は周囲の回路や基板までもが故障します。
数円〜十数円の保護部品でそれを防げるのであれば、**「搭載しない理由はない」**とも言えます。
実際に回路図を描いてみた
「PチャネルMOSFETによる逆接続保護回路」の簡単な例です:
+Vin(正電源)
│
│
┌─▼───┐
│ P-MOSFET │
└─┬───┘
│
├───→ DC/DCコンバータのVin端子
│
GND(負電源)
※ゲートは抵抗でGNDにプルダウン
このように、PチャネルMOSFETを1個追加するだけで、
逆接続時には自動的に電流を遮断し、ICの破壊を防ぐことができます。
しかも、MOSFETは順方向に動作している間、電圧降下(ドロップ)も非常に小さく(数十mV程度)、電力ロスも最小限です。
[quads id=2]
まとめ
「トランジスタによる低ドロップ型の逆接続保護回路を追加する」とは、
回路を逆につないでしまっても壊れないようにしつつ、効率も犠牲にしないスマートな設計方法です。
DC/DCコンバータを使った設計においては、信頼性を高めるための基本的な工夫のひとつとして、多くの実装例で採用されています。
-
DC/DCコンバータは逆接続に非常に弱いため、保護回路はあらかじめ設計に含めるべき
-
トランジスタ(MOSFET)を使った低ドロップ型保護は、効率と安全性の両立が可能
-
「壊れるかもしれない」より、「壊れない仕組みを作る」設計がプロフェッショナル
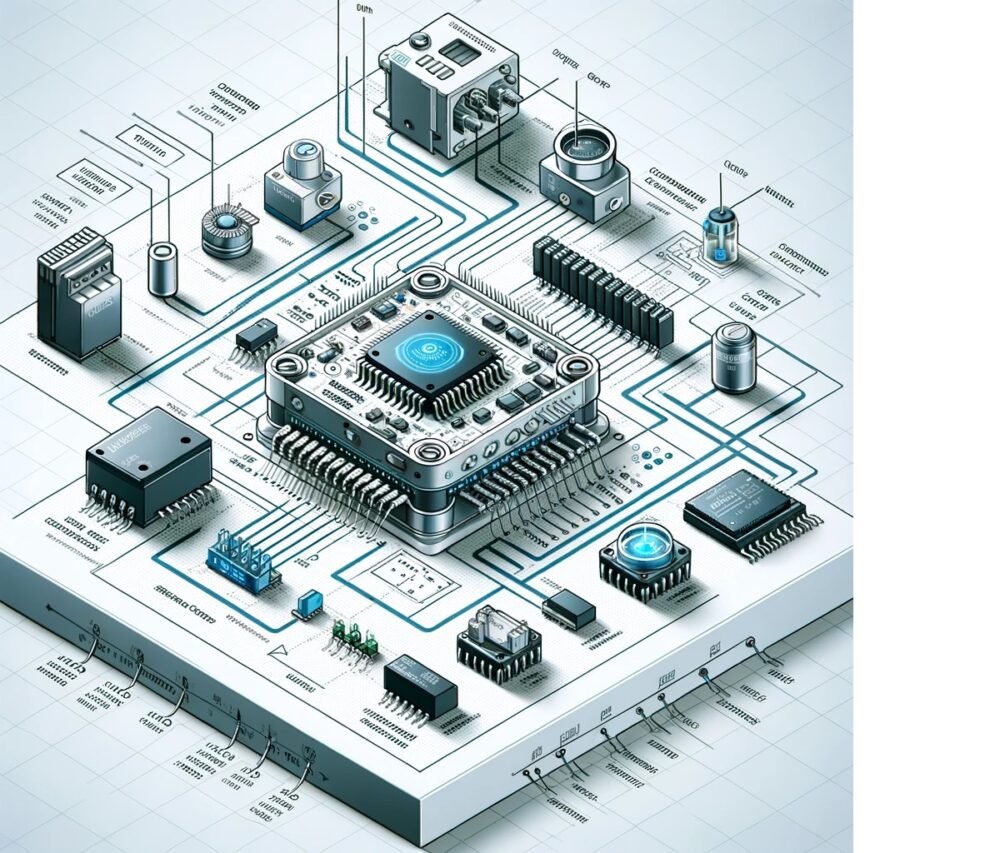
コメント